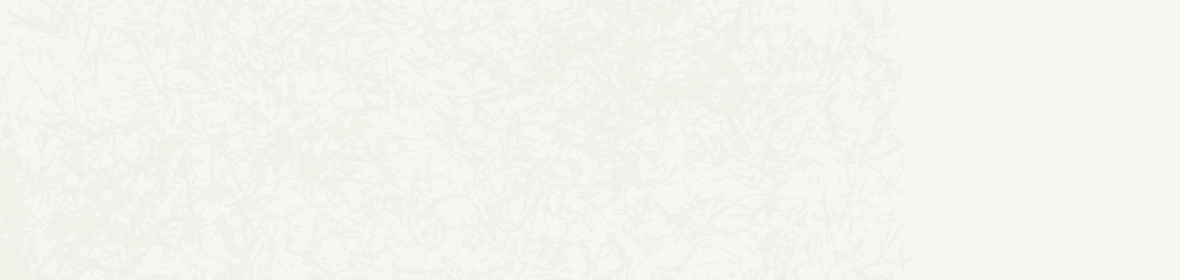
理 事 長林田 直樹 Naoki Hayashida

会員の皆様、その他関係の皆様方におかれましては、日頃よりセンターの事業運営等につきまして、格別のご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。この場をお借りして改めて感謝を申し上げます。
令和6年能登半島地震から1年半が経過しました。改めて被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。復旧復興が着実に進み、一日も早く平穏な日常が戻りますことを願っております。
当センターでは、「農業集落排水施設災害対策応援に関する協定」に基づいて被災市町からの要請に応じて、発災直後から会員の皆様方からのご協力をいただきながら当センターの職員を含めた応援人員の派遣調整等を行いつつ、被災調査等に当たってまいりました。引き続き、被災された農業集落排水施設の早期の復旧に貢献できるよう努めてまいります。
センターの事業運営につきましては、まず、令和6年度における当センターの業務実施について、農村環境や農業集落排水事業等、農業農村整備事業をめぐる情勢の変化を踏まえつつ、地域のニーズに対応するべく、体制を整えながら進めてまいりました。
皆様方のご理解・ご協力を得て、順調に所定の成果を得ることができましたことを深く感謝申し上げます。
次に、令和7年度のセンターの業務実施について、大きく二つのポイントについて述べさせていただきます。
一つは集排施設についてですが、設置されてから30~40年が経過していて施設の更新の必要性が高まっています。更新に当たっては農村地域の人口動態を踏まえた施設規模の見直し、効率性の高い省エネ機器などの新技術や太陽光発電の導入などによる維持管理費の節減に関して、管理主体である自治体の関心はこれまでになく高まっています。このため、農林水産省が創設した制度である「維持管理適正化計画」の策定に対する支援業務につきましては、本年度も多くのご要望をいただいているところであり、府県土連の皆様と連携協力させていただきながら、会員の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。集排施設を積極的に導入した時代から数十年を経て、効率性、経済性などに重点を置いた新しい事業展開の時代が、少しずつしかし確実に始まっていると感じており、それらに応えられるよう取り組んでまいります。
二つ目は農村地域の環境保全の取組についてです。平成3年にセンターの前身の1つである「農村環境整備センター」が設立されて34年が経過し、全国の環境保全の取組もしっかり定着しています。ただ取組のルーティン化、熱意の低下といった傾向もみられ、水田魚道や多自然型水路など環境に配慮した施設の管理が粗放化するといった事態も生じるようになってまいりました。
一方で世界的には、自然生態系の保全が地球規模の重要な課題であり強力な対策が必要であるとの共通認識が深まっています。直近では、2022年に発表された「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」において、「自然と共生する世界」を目指すことが打ち出され、2050年をゴールとする具体的なビジョンが示されました。日本においても、2023年3月に「生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定し、農林水産省においては2021年5月の「みどりの食料システム戦略」、2023年8月の「農林水産省生物多様性戦略」が発表されるなど、これまでになく農村地域における生物多様性に対する政府の姿勢が強く打ち出されています。
センターとしても設立の理念に立ち返り、美しい農村景観や農村地域の生物多様性を含む二次的自然環境を保全し、環境との調和を図るための調査研究や農村環境の維持・継承にもつながる地域活動である「田んぼの学校」支援や「田園自然再生活動の集い」などの自主事業にも気持ちを新たにして積極的に取り組んでまいります。
昨年6月、四半世紀ぶりに、「食料・農業・農村基本法」が、「食料安全保障の抜本的な強化」、「(食料システム全体の)環境と調和のとれた産業への転換」、「人口減少下における農業生産の維持・発展と農村の地域コミュニティの維持」の実現を目指して改正されました。本年4月には、これらの理念の実現に向け、「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されました。また、新基本法等も踏まえ、土地改良法が改正・施行され、農業生産基盤の保全に必要な施策として、申請によらない国等による基幹的な農業水利施設の更新事業の創設などが講じられ、新たな土地改良長期計画の策定作業も進められていると伺っております。これらの動向も注視していきたいと考えております。
今後とも、これまでの歩みを振り返りつつ、新たな次の時代に向けて会員の皆様の期待に応えていけるよう、会員ニーズを的確に把握し、農村地域の活性化・発展に貢献するため、また、災害時における支援体制の強化など役職員一丸となって取り組んでまいりたいと思っております。引き続き会員の皆様のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年7月
一般社団法人地域環境資源センター(JARUS)
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目34番4号
TEL:03-3432-5295 FAX:03-5425-2466
