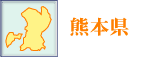
| ●扇棚田(産山村) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/10 | 2.1 ha |
| 推薦項目 | 国土の保全 生態系の保全 景観 |
| 推薦理由 | 国土の保全:原野の中にある扇田は、周辺の自然景観に融合して「阿蘇の草原」を形成しており、山間地の持つ特性を後世に伝え続ける。 生態系の保全:野の花の開花を促進する小動物の生息地であり、水の滞留はこの小動物に欠くことのできないものである。 景観:祖母の山々を遠望でき、杉等の周辺管理が行き届いているので素晴らしい景観となっている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 17 枚 | 水 源 | 井戸(湧水含む) |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 | |
| 開発起源 | 近世(戦国~江戸時代) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 3 戸 | 10a当収量 | 450 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.7 ha/戸 6 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 健康米として自家消費 | |||
| 特記事項の有無 | 肥後の赤牛の堆肥を投入、涼しいので防除も必要としない。 |
| ●日光の棚田(坂本村) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/5 | 2 ha |
 |
維持・保全・利活用状況 |
|
山間地の狭小な棚田で従来からの稲作を共同農作業で行っている。 |
| 推薦項目 | 景観 伝統文化の維持保全 |
| 推薦理由 | 景観:集落住民の共同農作業により棚田の形状保全に努めている。 伝統文化の維持保全:当地区では“はさ掛け”による伝統農法が継承されている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 232 枚 | 水 源 | 天水 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 石積 | |
| 開発起源 | 近世(戦国~江戸時代) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 18 戸 | 10a当収量 | 360 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.11 ha/戸 13 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | はさ掛け乾燥による品質向上を図る。 | |||
| 特記事項の有無 | 本地域では野石が少なく、米、粟等の農作物と野石を物々交換し、現在の棚田を築き上げたと伝えられている。 |
| ●天神木場の棚田(東陽村) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/5 | 2 ha |
 |
維持・保全・利活用状況 |
| 集落による農道の共同管理を行っている。 定期的に石積の除草を行っている。 |
| 推薦項目 | 景観 伝統文化の維持保全 |
| 推薦理由 | 景観:この地域は、昔ながらの“はさ掛け”により米の生産が行われているため、おいしいとの評判があり「箱石米」のブランド名が確立しつつある。 伝統文化の維持保全:伝統芸能「雨乞い太鼓」が保存会により継承されている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 60 枚 | 水 源 | ため池 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 石積 | |
| 開発起源 | 近世(戦国~江戸時代) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 12 戸 | 10a当収量 | 360 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.2 ha/戸 5 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | はさ掛け乾燥による品質向上を図る。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●美生の棚田(東陽村) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/10 | 1.3 ha |
 |
維持・保全・利活用状況 |
| 畑作深層地下水事業により地下水は確保されており地区組合で管理されている。 定期的に石積の除草を行っている。 |
| 推薦項目 | 生態系の保全 伝統文化の維持保全 |
| 推薦理由 | 生態系の保全:この地域内を流れる河川は、“かじか蛙”の生息地であり、水質の保全、河川環境の保全に努めている。 伝統文化の維持保全:当地区で栽培されている「しょうが」の品質は、市場での評価も高く、その栽培技術が継承されている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 52 枚 | 水 源 | 井戸 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 石積 | |
| 開発起源 | 近世(戦国~江戸時代) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 8 戸 | 10a当収量 | 4000 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.2 ha/戸 7 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 以前は稲を栽培で、現在は転作で“しょうが”の栽培を行い本村の基幹作物となっている。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●大作山の千枚田(龍ヶ岳町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/7 | 13 ha |
 |
維持・保全・利活用状況 |
| 苗代の時期に全員で草刈りを行っている。 交流活動に関しては、現在町のウォークラリーの際に田んぼ一画のレンゲ草を満喫してもらっているが、都会の子供たちにも田植え、レンゲ草刈りをしてもらう。 |
| 推薦項目 | 景観 伝統文化の維持保全 |
| 推薦理由 | 景観:棚田の形状的な美しさ、四季を通じて目を楽しませてくられる。 伝統文化の維持保全:地域独特の祭礼神事として「観音祭り」があり、大作山地区の人の棒踊りも行われる。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 110 枚 | 水 源 | 天水 河川 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 | |
| 開発起源 | 中世(平安~室町) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 19 戸 | 10a当収量 | 400 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.5 ha/戸 5.8 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 特になし。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |