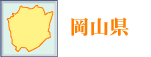
| ●北庄(久米南町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/7.5 | 88 ha |
 |
維持・保全・利活用状況 |
| ・本棚田は、北庄地区内の3営農組合が中心となって耕作されている。 ・農産物は、天然棚田米の生産が行われているが、今後は面積の拡大を進める。 ・溜め池・水路の管理は、各水利組合で管理している。 ・昨年から棚田まつりを実施しているが、内容充実し消費者との結びつきを強化する。 |
| 推薦項目 | 景観 伝統文化の維持保全 |
| 推薦理由 | 国土の保全:本地域は、町の北西部に位置し、旭川の支流誕生寺川の水源である。隣接する中央町は吉井川水系で、両河川の分水嶺に位
置する。溜め池が多く点在するが、耕作や日々の見回りにより災害の未然の防止に大きな役割を果
たしている。 景観:久米南町の代表的な景観の一つとなっているのみならず、国道53号線からも遠望できる。「耕して天に至る」の表現の如く地域の最高峰に溜め池があり、周辺の山と良く調和している。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 2700 枚 | 水 源 | 溜め |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 石積 | |
| 開発起源 | 近代(明治~昭和20年) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 92 戸 | 10a当収量 | 530 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.96 ha/戸 29 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 |
有機減農薬天然棚田米の生産販売。 |
|||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●上籾(久米南町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/7 |
22 ha |
 |
維持・保全・利活用状況 |
| ・本棚田は、上籾地区の営農組合が中心となって耕作されている。 ・農産物は、有機無農薬棚田米の生産が行われているが、今後は面積の拡大を進める。 ・溜め池・水路の管理は、各水利組合で管理している。 ・消費者との交流会を実施しているが、内容充実し、結びつきを強化する。 |
| 推薦項目 | 国土の保全 生態系の保全 |
| 推薦理由 | 国土の保全:本地域は、町の北西部に位置し、旭川の支流誕生寺川の水源である。溜め池が多く点在するが耕作や日々の見回りにより災害の未然の防止に大きな役割を果
たしている。 景観:久米南町の代表的な景観の一つとなっている。天気の良いときには瀬戸内海まで遠望できる。 「耕して天に至る」の表現の如く地域の最高峰に溜め池があり、周辺の山と良く調和している。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 1000 枚 | 水 源 | 溜め池 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 石積 | |
| 開発起源 | 近代(明治~昭和20年) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 42 戸 | 10a当収量 | 530 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.52 ha/戸 24 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 有機減農薬天然棚田米の生産販売。 棚田まつりの実施による消費者との交流。 |
|||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●小山(旭町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/10 | 5.5 ha |
 |
維持・保全・利活用状況 |
| ・本棚田は、地元小山集落だけで個々に耕作されている。 ・営農についても、集落内農業者だけでなく、集落外農業者により管理されていて、地域の活性化及び耕作の継続が見込める。 |
| 推薦項目 | 景観 |
| 推薦理由 | 景観:山間部に位置し、周辺の山と良く調和して、四季様々な景観を作っている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 30 枚 | 水 源 | 天水 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 | |
| 開発起源 | 近代(明治~昭和20年)。 | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 5 戸 | 10a当収量 | 480 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 1 ha/戸 6 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 特になし。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●大垪和(中央町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/5 | 42.2 ha |
| 推薦項目 | 国土の保全 景観 |
| 推薦理由 | 国土の保全:当地域は過疎高齢化が町内でも特に進んでいるが、生産組合の組織・機械化作業の委託・共同作業等により、棚田の荒廃防止に努めている。また、美しい棚田の景観の裏面
には苦労を強いられる中で、棚田を守る人達の努力があることも理解してもらいたい。 景観:当地区は標高400mの山間地に位置し大きなな谷全体に、360度の棚田がすり鉢状に42.2ha850枚で広がっている。また、大自然と歴史が多くあり、中でも中世密教の神秘さを今にとどめた地区であり、棚田とあわせての見学者も多い。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 850 枚 | 水 源 | 天水 |
| 事業導入 | 有 | 法面構造 | 土羽 | |
| 開発起源 | 近代(明治~昭和20年) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 64 戸 | 10a当収量 | 420 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.366 ha/戸 13 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 棚田天然枚(有機低農薬の推進) | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |