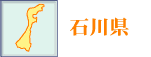
| ●奥山田(津幡町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/20 | 1.7 ha |
| 維持・保全・利活用状況 | |
| 本棚田は、地元九折集落が中心となり耕作されており、耕作放棄地も減少している。 |
| 推薦項目 | 国土保全 |
| 推薦理由 | 国土保全:本地域は地滑り地帯であるが、耕作や日々の見回りにより、災害の未然防止に大きな役割を果 たしている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 25 枚 | 水 源 | ため池 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 | |
| 開発起源 | 近代(明治~昭和20年) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 6 戸 | 10a当収量 | 440 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.28 ha/戸 4.2 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 特になし。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●大笹波水田(富来町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/20 | 1.15 ha |
| 推薦項目 | 国土保全 景観 |
| 推薦理由 | 国土保全:本地域の農地は連担性が低く、危峻な地形に立地しているが、法面
、畦畔除草作業等の維持管理には関心が深く、災害の未然防止に大きな役割を果
たしている。 景観:日本海と集落が周辺の山々とよく調和して、秀逸な景観を作っている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 180 枚 | 水 源 | ため池 |
| 事業導入 | 有 | 法面構造 | 土羽 | |
| 開発起源 | 近代(明治~昭和20年) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 41 戸 | 10a当収量 | 460 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.38 ha/戸 4.4 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | ・地域内で活動する無農薬栽培クループの活動推進。 ・有機栽培による棚田オーナー制(ジャガイモ)の実施に伴う都市住民との交流推進。 |
|||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●白米の千枚田(輪島市) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/3.06 | 1.2 ha |
| 推薦項目 | 国土保全 景観 伝統・文化の維持・保全 |
| 推薦理由 | 国土保全:本地域は、地滑り地帯であるが、水路を整備し、耕作や日々の見回りによって災害の未然防止に大きな役割を果
たしている。 景観:本棚田は、高洲山の山裾が日本海に流れ込むような急斜面を切り開いて耕され、わずか1.2ha余りの面 積に2千枚余の田が耕作され、田一枚の平均面積が1.8坪である。「蓑の下耕し残る田一枚」と詠われるほどである。畦が描く幾何学模様が、紺碧の水平線に浮かぶ七ツ島の島影や海岸線に砕ける白い 波頭と調和して、奥能登を代表する美しい景観を作っている。 伝統・文化の維持・保全:本棚田は、能登の厳しい地形や自然を克服しようとした先祖の努力・執念が結晶したものであり、これを多くの人々の手で継承保存しようとすることは、奥能登の伝統・文化を保存しようとする上で非常に意義深いことといえる。水あて(畦の一部を切り込み上方の田より順次下方の田へ水を導く水利方法)や、はざかけ等の伝統的耕作方法の保存・伝承をつづけている。千枚田を訪れる年間観光客は50万人を数える。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 2092 枚 | 水 源 | 河川(渓流含) |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 土羽 | |
| 開発起源 | 近世(戦国~江戸) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 11 戸 | 10a当収量 | 388 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.11 ha/戸 190 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 千米田ブランド米販売(JAおおぞら農業協同組合)。 千枚田ブランドの地酒販売。 地元特産、野菜・山菜・海産物等の販売。 |
|||
| 特記事項の有無 | なし。 |